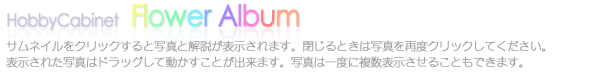ヤバイ(野梅)
Prunus mume バラ科
梅は中国が原産です。野梅は原種に近い種類で、花や葉は小ぶりですが香りの良い早咲きの花です。
Prunus mume バラ科
梅は中国が原産です。野梅は原種に近い種類で、花や葉は小ぶりですが香りの良い早咲きの花です。
アオジク(青軸)
Prunus mume バラ科
ガクと若い枝が緑色をしています。そこから「青軸」と言われるようになったのでしょうか?(これは私の推測。笑)花もきれいですが、梅の実も梅干しや梅酒にと使えるエライやつです。
Prunus mume バラ科
ガクと若い枝が緑色をしています。そこから「青軸」と言われるようになったのでしょうか?(これは私の推測。笑)花もきれいですが、梅の実も梅干しや梅酒にと使えるエライやつです。
アリアケスミレ(有明菫)
Viola betonicifolia var. albescens スミレ科
日当たりの良い草地や田畑・湿地に生える多年草です。花の色には変化が多く、紫色のスジのある白色の花を咲かせることが多いですが、ほとんど白色と言うこともあります。この花の色の変化を明け方の空の色の変化に見立てたことが名前の由来です。
Viola betonicifolia var. albescens スミレ科
日当たりの良い草地や田畑・湿地に生える多年草です。花の色には変化が多く、紫色のスジのある白色の花を咲かせることが多いですが、ほとんど白色と言うこともあります。この花の色の変化を明け方の空の色の変化に見立てたことが名前の由来です。
ツボスミレ(坪菫)
Viola verecunda スミレ科
山地、草地、林などのやや湿ったところに生える多年草です。葉はハート形していて唇弁には紫のスジが入ります。坪菫(ツボスミレ)の「坪」とは庭のことで、庭に生えるスミレと言う意味です。そして、タチツボスミレに次いでよく見かける日本を代表するスミレのひとつでもあります。
Viola verecunda スミレ科
山地、草地、林などのやや湿ったところに生える多年草です。葉はハート形していて唇弁には紫のスジが入ります。坪菫(ツボスミレ)の「坪」とは庭のことで、庭に生えるスミレと言う意味です。そして、タチツボスミレに次いでよく見かける日本を代表するスミレのひとつでもあります。
オトメスミレ(乙女菫)
Viola grypoceras f. purprellocalcarata スミレ科
Viola grypoceras f. purprellocalcarata スミレ科
ハクモクレン(白木蓮)
Magnolia heptapeta モクレン科
モクレンは中国が原産の木で庭木としてよく植えられて、3月〜4月にかけて芳香のある花を咲かせます。モクレンは花の色によって「白木蓮」「紫木蓮」と区別をされています。
Magnolia heptapeta モクレン科
モクレンは中国が原産の木で庭木としてよく植えられて、3月〜4月にかけて芳香のある花を咲かせます。モクレンは花の色によって「白木蓮」「紫木蓮」と区別をされています。
アセビ(馬酔木)
Pieris japonica ツツジ科
馬が食べるとお酒に酔ったような状態になるところから付いた名前です。3月〜4月にかけてスズランのような花を咲かせます。
Pieris japonica ツツジ科
馬が食べるとお酒に酔ったような状態になるところから付いた名前です。3月〜4月にかけてスズランのような花を咲かせます。
ドウダンツツジ(満天星躑躅)
Enkianthus perulatus ツツジ科
ツツジ科の落葉低木。4〜5月にスズランに似た釣り鐘状の白い花を咲きます。名前を知るまでツツジの一種だとは気付きませんでした。
Enkianthus perulatus ツツジ科
ツツジ科の落葉低木。4〜5月にスズランに似た釣り鐘状の白い花を咲きます。名前を知るまでツツジの一種だとは気付きませんでした。
ダイコン(大根)
Raphanus sativus アブラナ科
Raphanus sativus アブラナ科
ハナツルボラン(花蔓穂蘭)
Asphodelus fistulosus ユリ科
地中海沿岸が原産の宿根多年草。日本には園芸品種として渡来してきましたが、一部には帰化したものもあります。オオツルボ同様の星形の白い可憐な花を咲かせるのですが、私にはヒトデに見えてしまう。。。目がおかしい?(笑)
Asphodelus fistulosus ユリ科
地中海沿岸が原産の宿根多年草。日本には園芸品種として渡来してきましたが、一部には帰化したものもあります。オオツルボ同様の星形の白い可憐な花を咲かせるのですが、私にはヒトデに見えてしまう。。。目がおかしい?(笑)
スナップエンドウ(Snappy)
Pisum sativum マメ科
アメリカからやってきたお豆の品種で、サヤが柔らかいのでサヤごと食べられます。スナックエンドウとも呼ばれていますが、農水省ので定められた統一名称は「スナップエンドウ」です。ちょっと話しは逸れますが、この統一名称の中にはゴーヤもあるのですが、こちらは「ニガウリ」が正式名称なんですって!
Pisum sativum マメ科
アメリカからやってきたお豆の品種で、サヤが柔らかいのでサヤごと食べられます。スナックエンドウとも呼ばれていますが、農水省ので定められた統一名称は「スナップエンドウ」です。ちょっと話しは逸れますが、この統一名称の中にはゴーヤもあるのですが、こちらは「ニガウリ」が正式名称なんですって!
ソラマメ(空豆)
Vicia faba マメ科
1年草または越年草です。名前の由来はサヤが空に向かって付くので空豆。(笑)単純ですね。昨年、よそのお家の畑に空豆が植えてあったので、それを見ながらこの名前の由来を夫に言ったところ、夫は知りませんでした。と、言うか、それまで畑で育っている空豆を見たことがなかったのでした。ちなみに私もでしたが。(笑)
Vicia faba マメ科
1年草または越年草です。名前の由来はサヤが空に向かって付くので空豆。(笑)単純ですね。昨年、よそのお家の畑に空豆が植えてあったので、それを見ながらこの名前の由来を夫に言ったところ、夫は知りませんでした。と、言うか、それまで畑で育っている空豆を見たことがなかったのでした。ちなみに私もでしたが。(笑)
 モミジイチゴ(紅葉苺)
モミジイチゴ(紅葉苺)Rubus palmatus var. coptophyllus バラ科
葉っぱがモミジに似ているので「モミジイチゴ」です。花は下向きに咲き、黄色い実を付けるところから「黄苺」の別名もありますが、『木苺』ではありません。中部地方以北に分布しているのが「モミジイチゴ」と呼ばれているようで、ここは中国地方ですし、写真では見にくいですが葉っぱの真ん中が長かったので、これは「ナガバノモミジイチゴ」だと思います。
 クサイチゴ(草苺)
クサイチゴ(草苺)Rubus hirsutus バラ科
落葉低木ではありますが、草のように横に這って広がります。3月の終わりから4月にかけて白い花を咲かせ、5月の終わり頃にラズベリーの様な形の赤い可愛い実を付けます。この実は食べらます。生で食べても美味しいですが、ジャムにするとこれまた美味しいです。
ノイバラ(野茨)
Rosa multiflora バラ科
Rosa multiflora バラ科
ユキヤナギ(雪柳)
Spiraea thunbergii バラ科
落葉低木で柳のようにしだれた枝にいっぱいの小さな白い花を咲かせます。その様子は遠くから見ると雪が降り積もったように見えます。ですが、花が咲くのは春なんですけどね。(笑)
Spiraea thunbergii バラ科
落葉低木で柳のようにしだれた枝にいっぱいの小さな白い花を咲かせます。その様子は遠くから見ると雪が降り積もったように見えます。ですが、花が咲くのは春なんですけどね。(笑)
オランダミミナグサ(阿蘭陀耳菜草)
Cerastium glomeratum ナデシコ科
ヨーロッパ原産の越年草。日当たりの良い道端や田畑などに普通に生えています。白色の5弁花をつけ、先端は2つに切れ込んでいます。茎や葉は黄色の毛が密生していて毛深いです。(笑)葉っぱの形がネズミの耳の形に似ているところが名前の由来です。
Cerastium glomeratum ナデシコ科
ヨーロッパ原産の越年草。日当たりの良い道端や田畑などに普通に生えています。白色の5弁花をつけ、先端は2つに切れ込んでいます。茎や葉は黄色の毛が密生していて毛深いです。(笑)葉っぱの形がネズミの耳の形に似ているところが名前の由来です。
ハコベ(繁縷)
Stellaria media ナデシコ科
道端や田などにふつうに生えていて、花弁は5枚ですがV字に深く切れ込んでいるので10枚にも見えます。春の七草の1つでもあります。小鳥も好んで食べますが、私も子供の頃飼っていたインコや文鳥に庭から摘んであげていた覚えがあります。
Stellaria media ナデシコ科
道端や田などにふつうに生えていて、花弁は5枚ですがV字に深く切れ込んでいるので10枚にも見えます。春の七草の1つでもあります。小鳥も好んで食べますが、私も子供の頃飼っていたインコや文鳥に庭から摘んであげていた覚えがあります。
ノミノフスマ (蚤の衾)
Stellaria alsine var. undulata ナデシコ科
荒れ地や田畑にふつうに生えています。花は白色の5弁花ですが、V字に深く切れ込んでいるので10枚にも見えます。花はハコベにもよく似ていますが、ノミノフスマは全体に無毛です。小さな葉っぱを蚤のフスマ(お布団)に例えたことが名前の由来です。
Stellaria alsine var. undulata ナデシコ科
荒れ地や田畑にふつうに生えています。花は白色の5弁花ですが、V字に深く切れ込んでいるので10枚にも見えます。花はハコベにもよく似ていますが、ノミノフスマは全体に無毛です。小さな葉っぱを蚤のフスマ(お布団)に例えたことが名前の由来です。
ツメクサ(爪草)
Sagina japonica ナデシコ科
道端や庭に普通に生えています。地面を這うように根元から枝を分け、葉の脇から長い柄を出して小さな白色の花を咲かせます。葉は先が尖っていて鳥の爪に似ている事が名前の由来です。ツメクサを乾燥させて解熱や皮膚病などに薬用として使えます。
Sagina japonica ナデシコ科
道端や庭に普通に生えています。地面を這うように根元から枝を分け、葉の脇から長い柄を出して小さな白色の花を咲かせます。葉は先が尖っていて鳥の爪に似ている事が名前の由来です。ツメクサを乾燥させて解熱や皮膚病などに薬用として使えます。
ノハラツメクサ(野原爪草)
Spergula arvensis L. ナデシコ科
畑や空き地などに生えるヨーロッパ原産の帰化植物です。葉っぱは松の葉のような細いものでスギナの様です。よく似た花にオオツメクサがありますが、見分け方は種子を見ないと分かりづらく、種子の表面に突起がないものがオオツメクサです。ノハラツメクサには白色の突起があります。
Spergula arvensis L. ナデシコ科
畑や空き地などに生えるヨーロッパ原産の帰化植物です。葉っぱは松の葉のような細いものでスギナの様です。よく似た花にオオツメクサがありますが、見分け方は種子を見ないと分かりづらく、種子の表面に突起がないものがオオツメクサです。ノハラツメクサには白色の突起があります。
ノミノツヅリ(蚤の綴り)
Arenaria serpyllifolia ナデシコ科
道端や荒れ地などに生える1年草〜越年草で全世界に分布しています。綴りとは、葉っぱをノミの着る粗末な衣に例えたことが名前の由来です。
Arenaria serpyllifolia ナデシコ科
道端や荒れ地などに生える1年草〜越年草で全世界に分布しています。綴りとは、葉っぱをノミの着る粗末な衣に例えたことが名前の由来です。
スズラン(鈴蘭)
Convallaria keiskei ユリ科
Convallaria keiskei ユリ科
アメリカフウロ(亜米利加風露)
Geranium carolinianum フウロソウ科
アメリカ原産の帰化植物です。茎には軟毛が生えてふさふさした感じです。よく似た花のゲンノショウコも同じフウロソウ科の植物です。ゲンノショウコは健胃整腸剤の効能を持っていますが、仲間である「アメリカフウロ」も主成分が同じなので、同じように民間薬として使えるようです。
Geranium carolinianum フウロソウ科
アメリカ原産の帰化植物です。茎には軟毛が生えてふさふさした感じです。よく似た花のゲンノショウコも同じフウロソウ科の植物です。ゲンノショウコは健胃整腸剤の効能を持っていますが、仲間である「アメリカフウロ」も主成分が同じなので、同じように民間薬として使えるようです。
シロミミナグサ(白耳菜草)
Cerastium tomentosum ナデシコ科
ナデシコ科の多年草。5〜6月に真っ白な花を咲かせ、葉も銀白色ということもあり、別名ナツユキソウ(夏雪草)とも呼ばれています。ほふく性のある植物であり、葉を観賞しても美しいのでグランドカバーに適しています。
Cerastium tomentosum ナデシコ科
ナデシコ科の多年草。5〜6月に真っ白な花を咲かせ、葉も銀白色ということもあり、別名ナツユキソウ(夏雪草)とも呼ばれています。ほふく性のある植物であり、葉を観賞しても美しいのでグランドカバーに適しています。
オーニソガラム(大甘菜)
Ornithogalum umbellatum ユリ科
ヨーロッパ原産で明治時代に渡来した宿根植物です。お日さまが出ている明るいときに花を咲かせ、夕方暗くなってくると花を閉じて蕾のように戻ります。白い可憐な花の形が星に似ていることからキリスト生誕を知らせたベツレヘムの星にも例えられた別名もあります。
Ornithogalum umbellatum ユリ科
ヨーロッパ原産で明治時代に渡来した宿根植物です。お日さまが出ている明るいときに花を咲かせ、夕方暗くなってくると花を閉じて蕾のように戻ります。白い可憐な花の形が星に似ていることからキリスト生誕を知らせたベツレヘムの星にも例えられた別名もあります。
ネモフィラ マクラタ (five spot)
Nemophila maculata ハゼリソウ科
耐寒性の1年草でカルフォルニアが原産地です。ネモフィラとはギリシア語で「森を愛する」と言う意味です。ネモフィラは園芸種ですが、この花のように白い花の先に青いアクセントが付く「マクラタ」の他にも水色の花びらに中央が白い「インシグニス」、黒い花弁に花弁の周りが白いペニーブラックなどがあります。
Nemophila maculata ハゼリソウ科
耐寒性の1年草でカルフォルニアが原産地です。ネモフィラとはギリシア語で「森を愛する」と言う意味です。ネモフィラは園芸種ですが、この花のように白い花の先に青いアクセントが付く「マクラタ」の他にも水色の花びらに中央が白い「インシグニス」、黒い花弁に花弁の周りが白いペニーブラックなどがあります。
スノーフレーク(鈴蘭水仙)
Leucojum aestivum Leucojum ヒガンバナ科
ヒガンバナ科の多年草で中部ヨーロッパ・地中海沿岸が原産国の清楚な感じのするお花です。葉と球根がスイセンに、花はスズランに似ていることから別名に「スズランスイセン」と言われていますが、和名では「オオマツユキソウ」と言います。よく似た花で「スノードロップ」がありますが、こちらの和名は「マツユキソウ」。花の大きさの違いでこのような名前が付いたようです。
Leucojum aestivum Leucojum ヒガンバナ科
ヒガンバナ科の多年草で中部ヨーロッパ・地中海沿岸が原産国の清楚な感じのするお花です。葉と球根がスイセンに、花はスズランに似ていることから別名に「スズランスイセン」と言われていますが、和名では「オオマツユキソウ」と言います。よく似た花で「スノードロップ」がありますが、こちらの和名は「マツユキソウ」。花の大きさの違いでこのような名前が付いたようです。
ミツバウツギ(三葉空木)
Staphylea bumalda ミツバウツギ科
落葉低木。名前の通り葉が3枚一組の三出複葉からなっています。幹が「空ろ」がらんどうと言う意味からも名前が由来しています。春の若芽は食べられます。
Staphylea bumalda ミツバウツギ科
落葉低木。名前の通り葉が3枚一組の三出複葉からなっています。幹が「空ろ」がらんどうと言う意味からも名前が由来しています。春の若芽は食べられます。
ミヤマガマズミ(深山莢迷)
Viburnum wrightii スイカズラ科
落葉低木。金槌の柄やザルなどにも使われる木です。4月下旬頃から純白の花を咲かせ、10月頃には赤い実を付けます。鳥たちも好んで食べますが、酸っぱい実なので果実酒にすると美味しいそうです。花がそっくりなガマズミも赤い実を付けますが、こちらは甘酸っぱく、昔なら子供のおやつだったそうです。二つの見分け方は、葉の先が鋭くとがり葉柄に絹のような毛が生えているのが「ミヤマガマズミ」です。あと、実を食べて甘酸っぱく美味しいのは「ガマズミ」ですね。(笑)
Viburnum wrightii スイカズラ科
落葉低木。金槌の柄やザルなどにも使われる木です。4月下旬頃から純白の花を咲かせ、10月頃には赤い実を付けます。鳥たちも好んで食べますが、酸っぱい実なので果実酒にすると美味しいそうです。花がそっくりなガマズミも赤い実を付けますが、こちらは甘酸っぱく、昔なら子供のおやつだったそうです。二つの見分け方は、葉の先が鋭くとがり葉柄に絹のような毛が生えているのが「ミヤマガマズミ」です。あと、実を食べて甘酸っぱく美味しいのは「ガマズミ」ですね。(笑)
コデマリ(小手毬)
Spiraea cantoniensis バラ科
中国原産の落葉低木です。たくさんの小さな白い花が毬状に集まっていることから江戸時代に名付けられました。
Spiraea cantoniensis バラ科
中国原産の落葉低木です。たくさんの小さな白い花が毬状に集まっていることから江戸時代に名付けられました。
シロバナタンポポ (白花蒲公英)
Taraxacum hondoense キク科
道端や人家の近くに生える多年草。西日本に多いタンポポで、黄色のセイヨウタンポポなどが帰化植物が入ってくるまでは中国地方ではシロバナタンポポしか咲いていませんでした。シロバナタンポポは単為生殖で繁殖するので、各地のものすべて同一の遺伝子組成を持っています。
Taraxacum hondoense キク科
道端や人家の近くに生える多年草。西日本に多いタンポポで、黄色のセイヨウタンポポなどが帰化植物が入ってくるまでは中国地方ではシロバナタンポポしか咲いていませんでした。シロバナタンポポは単為生殖で繁殖するので、各地のものすべて同一の遺伝子組成を持っています。
ノースポール
Chrysanthemum paludosum キク科
Chrysanthemum paludosum キク科
マーガレット(木春菊)
Argyranthemum frutescens キク科
キク科の多年草。カナリア諸島が原産で、若い葉は春菊に似ていますが、成長すると茎が木質化するところから和名を「木春菊」と言います。ギリシャ語のマルガリテース(真珠)がマーガレットの名前の由来とも言われています。私はマーガレットを見ると、白井貴子の歌「野生のマーガレット」が頭の中で流れてしまいます。ああ、年がバレる。(笑)
Argyranthemum frutescens キク科
キク科の多年草。カナリア諸島が原産で、若い葉は春菊に似ていますが、成長すると茎が木質化するところから和名を「木春菊」と言います。ギリシャ語のマルガリテース(真珠)がマーガレットの名前の由来とも言われています。私はマーガレットを見ると、白井貴子の歌「野生のマーガレット」が頭の中で流れてしまいます。ああ、年がバレる。(笑)
ペーパーカスケード
Helipterum anthemoides 'Paper Cascade' キク科
キク科の多年草。ヘリクサムの花びらは紙のように薄くカサカサしています。「ハナカンザシ」の名前でも流通していますが、本当の「ハナカンザシ (Helipterum roseum)」とは違うので花言葉も違い、ペーパーカスケードの花言葉は「小さな思いで」です。ちなみにハナカンザシは「思いやり」。
Helipterum anthemoides 'Paper Cascade' キク科
キク科の多年草。ヘリクサムの花びらは紙のように薄くカサカサしています。「ハナカンザシ」の名前でも流通していますが、本当の「ハナカンザシ (Helipterum roseum)」とは違うので花言葉も違い、ペーパーカスケードの花言葉は「小さな思いで」です。ちなみにハナカンザシは「思いやり」。
カモミール(カミツレ)
Matricaria recutita・Chamaemelum nobil キク科
耐寒性の1年草。甘いリンゴのような香りのする植物です。鎮静作用やリラックス効果のあるハーブなので、夜の食後にお茶として飲んだりすると催眠効果にもなります。また月経・更年期の抗うつ作用にも良いとされています。
Matricaria recutita・Chamaemelum nobil キク科
耐寒性の1年草。甘いリンゴのような香りのする植物です。鎮静作用やリラックス効果のあるハーブなので、夜の食後にお茶として飲んだりすると催眠効果にもなります。また月経・更年期の抗うつ作用にも良いとされています。
イベリス(トキワナズナ)
Iberis sempervirens アブラナ科
イベリスは1年草と多年草の2種類があり、多年草の方は特に乾燥に強いです。また、茎の先にかたまって咲く白い花が砂糖菓子のようにも見えることから「キャンディタフト」の別名もあります。
Iberis sempervirens アブラナ科
イベリスは1年草と多年草の2種類があり、多年草の方は特に乾燥に強いです。また、茎の先にかたまって咲く白い花が砂糖菓子のようにも見えることから「キャンディタフト」の別名もあります。
タネツケバナ(種浸け花)
Cardamine flexuosa アブラナ科
田植えの前に行う種もみを水につける頃に花が咲くことが名前の由来です。若い葉は茹でて食べられ、辛みがあって美味しいそうです。
Cardamine flexuosa アブラナ科
田植えの前に行う種もみを水につける頃に花が咲くことが名前の由来です。若い葉は茹でて食べられ、辛みがあって美味しいそうです。
ナズナ(ナズ菜)
Capsella bursa-pastoris アブラナ科
道端や田畑などに生える越年草。実の形が三味線のバチに似ていることから「ペンペングサ」とも言われています。春の七草のひとつでもありますが、七草粥に入れて食べるようになったのは平安時代の頃からです。
Capsella bursa-pastoris アブラナ科
道端や田畑などに生える越年草。実の形が三味線のバチに似ていることから「ペンペングサ」とも言われています。春の七草のひとつでもありますが、七草粥に入れて食べるようになったのは平安時代の頃からです。
ヤブジラミ(藪虱)
Torilis japonica セリ科
野原や道端に普通に生えています。茎が分枝し枝先には花弁が5枚の白い花を咲かせます。果実には刺状の毛が密生し、それがひっつき虫のように服に付いたりします。その様子がシラミに似ていることから名前が付きました。「シラミ」みたいだなんて体が痒くなってきました。
Torilis japonica セリ科
野原や道端に普通に生えています。茎が分枝し枝先には花弁が5枚の白い花を咲かせます。果実には刺状の毛が密生し、それがひっつき虫のように服に付いたりします。その様子がシラミに似ていることから名前が付きました。「シラミ」みたいだなんて体が痒くなってきました。
シロバナマンテマ(白花マンテマ)
Silene gallica var. gallica ナデシコ科
ヨーロッパ原産の帰化植物です。咲き始めはピンクで徐々に白色に変わっていきます。パッと見ると、縦に一列に並んでいるように見える花ですが、よく見ると左右交互に花が付いています。シロバナマンテマは毛深い植物で、茎やガクには線毛が生えていて、触るとベタベタします。シロバナマンテマのガクって丸く膨らんでいるし、縞模様まであるのでまるでスイカみたいに見えてしまいます。
Silene gallica var. gallica ナデシコ科
ヨーロッパ原産の帰化植物です。咲き始めはピンクで徐々に白色に変わっていきます。パッと見ると、縦に一列に並んでいるように見える花ですが、よく見ると左右交互に花が付いています。シロバナマンテマは毛深い植物で、茎やガクには線毛が生えていて、触るとベタベタします。シロバナマンテマのガクって丸く膨らんでいるし、縞模様まであるのでまるでスイカみたいに見えてしまいます。
スズメノエンドウ(雀野豌豆)
Vicia hirsuta マメ科
道端や畑にふつうに生える越年草。葉の脇から花柄を伸ばし3〜4mmほどの白紫色の蝶形花を付けます。カラスノエンドウに比べてずっと小さいのでスズメノエンドウと言います。
Vicia hirsuta マメ科
道端や畑にふつうに生える越年草。葉の脇から花柄を伸ばし3〜4mmほどの白紫色の蝶形花を付けます。カラスノエンドウに比べてずっと小さいのでスズメノエンドウと言います。
カルミア(亜米利加石楠花)
Kalmia latifolia ツツジ科
北米原産でアメリカシャクナゲとも呼ばれます。花の時期は春。ツツジ科に属しますが花は全然似ていません。生クリームを絞り出したようなつぼみが可愛いです。スウェーデンの植物学者 Kalm氏の名前にちなんでカルミア(Kalmia)と名付けられました。
Kalmia latifolia ツツジ科
北米原産でアメリカシャクナゲとも呼ばれます。花の時期は春。ツツジ科に属しますが花は全然似ていません。生クリームを絞り出したようなつぼみが可愛いです。スウェーデンの植物学者 Kalm氏の名前にちなんでカルミア(Kalmia)と名付けられました。
ノコギリソウ(鋸草)
Achillea alpina キク科
セイヨウノコギリソウは色も豊富で白、ピンク、赤、黄色などの品種がありますが、自生している花は基本は白色です。葉っぱがノコギリの刃のようにギザギザなところから名前が付きました。セイヨウノコギリソウは治癒効果や止血効果のあるハーブでもあります。
Achillea alpina キク科
セイヨウノコギリソウは色も豊富で白、ピンク、赤、黄色などの品種がありますが、自生している花は基本は白色です。葉っぱがノコギリの刃のようにギザギザなところから名前が付きました。セイヨウノコギリソウは治癒効果や止血効果のあるハーブでもあります。
ハイノキ(灰の木)
Symplocos myrtacea ハイノキ科
この木は燃やすとすぐに灰になることから名前が付きました。この燃やした灰を染め物の媒染剤に使ったりします。
Symplocos myrtacea ハイノキ科
この木は燃やすとすぐに灰になることから名前が付きました。この燃やした灰を染め物の媒染剤に使ったりします。
ニワゼキショウ(庭石菖)
Sisyrinchium atlanticum アヤメ科
北アメリカ原産の多年草。明治の中期に日本に渡来し、今では各地に帰化して日当たりの良い道端や芝生などに生えています。アヤメ科なので花は1日しか咲きません。
Sisyrinchium atlanticum アヤメ科
北アメリカ原産の多年草。明治の中期に日本に渡来し、今では各地に帰化して日当たりの良い道端や芝生などに生えています。アヤメ科なので花は1日しか咲きません。
シロツメクサ(白詰草)
Trifolium repens マメ科
何処でも見かけるマメ科の多年草。5〜9月に花が咲きます。白詰草の名は、ガラスの器の詰め物としてこの乾し草が使われたことに由来するそうです。
Trifolium repens マメ科
何処でも見かけるマメ科の多年草。5〜9月に花が咲きます。白詰草の名は、ガラスの器の詰め物としてこの乾し草が使われたことに由来するそうです。
ドクダミ(毒矯 毒彩)
Houttuynia cordata ドクダミ科
空き地や林、家の日当たりの良くないところに生えている独特な臭いのある植物です。生薬としても有名で「十薬」の名前で知られています。葉の独特な臭いは嫌われがちですが、あの臭いにもちゃんと効能があり抗菌作用に優れています。湿疹・かぶれ・水虫などに効果がありますが、あの臭いの葉っぱを貼り付けるにはちょっと勇気がいりますね。(笑)それから白色に分類してしまいましたが、実は花は中央の黄色の部分で、白色の部分は花びらではありません。
Houttuynia cordata ドクダミ科
空き地や林、家の日当たりの良くないところに生えている独特な臭いのある植物です。生薬としても有名で「十薬」の名前で知られています。葉の独特な臭いは嫌われがちですが、あの臭いにもちゃんと効能があり抗菌作用に優れています。湿疹・かぶれ・水虫などに効果がありますが、あの臭いの葉っぱを貼り付けるにはちょっと勇気がいりますね。(笑)それから白色に分類してしまいましたが、実は花は中央の黄色の部分で、白色の部分は花びらではありません。
カキ(柿)
Diospyros kaki カキノキ科
カキの花は雄花、雌花とあります。これは雌花です。先日、実家の母との電話中に笑える話しを聞きました。干し柿が好きなので、毎年のように渋柿を買ってきては家で干し柿を作っている両親。味見と言ってはチョコチョコとつまみ食いをしているそうで(笑)、タネは庭に捨てていたらしいのです。その中の1つが発芽し今では10cmくらいの苗木になっているそうです。いつか我が家が田舎に家を買ったら、その柿の苗木をプレゼントするよ!と言われましたが、丁重にお断りしました。出来上がった干し柿をもらう方が嬉しいです!
Diospyros kaki カキノキ科
カキの花は雄花、雌花とあります。これは雌花です。先日、実家の母との電話中に笑える話しを聞きました。干し柿が好きなので、毎年のように渋柿を買ってきては家で干し柿を作っている両親。味見と言ってはチョコチョコとつまみ食いをしているそうで(笑)、タネは庭に捨てていたらしいのです。その中の1つが発芽し今では10cmくらいの苗木になっているそうです。いつか我が家が田舎に家を買ったら、その柿の苗木をプレゼントするよ!と言われましたが、丁重にお断りしました。出来上がった干し柿をもらう方が嬉しいです!
ヒメウズ(姫烏頭)
Semiaquilegia adoxoides キンポウゲ科
Semiaquilegia adoxoides キンポウゲ科
キンギンボク(金銀木)
2つセットで咲く花で、花の色が始めは白色でだんだんと黄色に変わります。その過程で白色と黄色の花が一緒に咲く様子から「キンギンボク」と名付けられました。黄色を金に、白色を銀に例えたのですね。ずいぶんと豪華になってますよ。(笑)
2つセットで咲く花で、花の色が始めは白色でだんだんと黄色に変わります。その過程で白色と黄色の花が一緒に咲く様子から「キンギンボク」と名付けられました。黄色を金に、白色を銀に例えたのですね。ずいぶんと豪華になってますよ。(笑)
ハクチョウゲ(白丁花)
Serissa japonica アカネ科
公園などに良く植栽されていて、5月〜6月に星型の小さい花を咲かせます。花は可愛いのですが、葉を揉むと悪臭がします。ずーと「白鳥花」かと思っていました。学名はJaponicaですが、原産は日本ではなくて東南アジアだそうです。
Serissa japonica アカネ科
公園などに良く植栽されていて、5月〜6月に星型の小さい花を咲かせます。花は可愛いのですが、葉を揉むと悪臭がします。ずーと「白鳥花」かと思っていました。学名はJaponicaですが、原産は日本ではなくて東南アジアだそうです。
マメグンバイナズナ(豆軍配薺)
Lepidium virginicum アブラナ科
北アメリカ原産の帰化植物で道端や荒れ地などに生えています。茎は20〜50cmになり枝先にたくさんの穂状の花序を出します。その頃には根生葉は枯れてなくなっています。似た花にグンバイナズナがありますが、果実(白い花の下の段に付いてる軍配型のもの)の大きさが違い、マメグンバイナズナは3mmほどと小さいので見分けられます。
Lepidium virginicum アブラナ科
北アメリカ原産の帰化植物で道端や荒れ地などに生えています。茎は20〜50cmになり枝先にたくさんの穂状の花序を出します。その頃には根生葉は枯れてなくなっています。似た花にグンバイナズナがありますが、果実(白い花の下の段に付いてる軍配型のもの)の大きさが違い、マメグンバイナズナは3mmほどと小さいので見分けられます。
カシワバアジサイ(柏葉紫陽花)
Hydrangea quercifolia. ユキノシタ科
葉の形が柏に似ているところから名前が付きました。アジサイは日本原産ですが、このカシワバアジサイは北アメリカが原産なので生まれが違う外人さんです。(笑)
Hydrangea quercifolia. ユキノシタ科
葉の形が柏に似ているところから名前が付きました。アジサイは日本原産ですが、このカシワバアジサイは北アメリカが原産なので生まれが違う外人さんです。(笑)
ネジキ(捩木)
Lyonia ovalifolia var. elliptica ツツジ科
落葉低木で幹がねじれていることからこの名前が付きました。ツツジ科の植物には有毒成分が含まれていて、ネジキには、けいれんや麻痺を引き起こす成分が含まれています。
Lyonia ovalifolia var. elliptica ツツジ科
落葉低木で幹がねじれていることからこの名前が付きました。ツツジ科の植物には有毒成分が含まれていて、ネジキには、けいれんや麻痺を引き起こす成分が含まれています。
ヒメジョオン(姫女苑)
Erigeron annuus キク科
北アメリカ原産の帰化植物で1年草〜越年草です。よく似た花にハルジオンがありますが、見分け方は「ヒメジョオン」は蕾がうなだれず茎の中は詰まっています。逆に「ハルジオン」は蕾がうなだれ茎の中には穴が空いています。荒れ地や道端などに良く生えている植物ですが、若芽のころは茹でたり天ぷらにしたら美味しいそうです。
Erigeron annuus キク科
北アメリカ原産の帰化植物で1年草〜越年草です。よく似た花にハルジオンがありますが、見分け方は「ヒメジョオン」は蕾がうなだれず茎の中は詰まっています。逆に「ハルジオン」は蕾がうなだれ茎の中には穴が空いています。荒れ地や道端などに良く生えている植物ですが、若芽のころは茹でたり天ぷらにしたら美味しいそうです。
カワラナデシコ(河原撫子)
Dianthus superbus var. longicalycinus ナデシコ科
日当たりの良い草地や河原などに咲く多年草。秋の七草の1つでもありますが、花は7月くらいから咲き始めます。春の七草のようにお粥にして食べるのかと思っていたら(笑)秋の七草とは目で楽しむもののようです。別名ヤマトナデシコ(大和撫子)。ピンクの花もありました。
Dianthus superbus var. longicalycinus ナデシコ科
日当たりの良い草地や河原などに咲く多年草。秋の七草の1つでもありますが、花は7月くらいから咲き始めます。春の七草のようにお粥にして食べるのかと思っていたら(笑)秋の七草とは目で楽しむもののようです。別名ヤマトナデシコ(大和撫子)。ピンクの花もありました。
クチナシ(梔)
Gardenia jasminoides アカネ科
6月〜7月に香りのよい白い花を咲かせます。果実は11月〜12月にがくをつけたまま黄赤に熟します。果実は乾燥させて染色に使います。
Gardenia jasminoides アカネ科
6月〜7月に香りのよい白い花を咲かせます。果実は11月〜12月にがくをつけたまま黄赤に熟します。果実は乾燥させて染色に使います。
センニンソウ(仙人草)
Clematis terniflora キンポウゲ科
キンポウゲ科の多年草。センニンソウには毒があり、馬や牛は食べません。間違って食べてしまうと歯が抜けてしまうとか。8月〜9月の花が終わり、10月頃になると果実が付いてくるのですが、長い白い毛も伸びて来て、その姿が仙人の髭に見立てたことが名前の由来です。茎などがクルクルと巻き付くこともなく、またツルが出てきて巻き付くわけでもないのですが、蔓性の落葉植物です。
Clematis terniflora キンポウゲ科
キンポウゲ科の多年草。センニンソウには毒があり、馬や牛は食べません。間違って食べてしまうと歯が抜けてしまうとか。8月〜9月の花が終わり、10月頃になると果実が付いてくるのですが、長い白い毛も伸びて来て、その姿が仙人の髭に見立てたことが名前の由来です。茎などがクルクルと巻き付くこともなく、またツルが出てきて巻き付くわけでもないのですが、蔓性の落葉植物です。
ペパーミント(西洋薄荷)
Mentha x piperita L. シソ科
とても丈夫で繁殖力がとても強い植物なので育てやすいのですが、気を付けないといけないのは種類の違うミントと一緒に寄せ植えなどにしてはいけないことです。ミントは交配しやすく、他のミントが近くにあると交配してしまい香りが変わってしまい全部同じ香りになってしまいます。お気を付け下さい。
Mentha x piperita L. シソ科
とても丈夫で繁殖力がとても強い植物なので育てやすいのですが、気を付けないといけないのは種類の違うミントと一緒に寄せ植えなどにしてはいけないことです。ミントは交配しやすく、他のミントが近くにあると交配してしまい香りが変わってしまい全部同じ香りになってしまいます。お気を付け下さい。
ガガイモ(がが芋)
Metaplexis japonica ガガイモ科
ガガイモ科の多年草。日当たりのよい野原などに生えるツル性の植物です。派の形が「ガガ」に似ていることが名前の由来ですが、「ガガ」とはスッポンのことです。栃木県の方言でスッポンのことを「コガミ」言うそうで、それが変化した言葉のようです。でも、(写真では見えませんが)葉っぱを見てもスッポンには見えないのですけど。先の尖ったところが、スッポンのシッポに似てるってことかな・・・。種子の綿毛は綿の代用として用いたり、止血効果もあるそうです。
Metaplexis japonica ガガイモ科
ガガイモ科の多年草。日当たりのよい野原などに生えるツル性の植物です。派の形が「ガガ」に似ていることが名前の由来ですが、「ガガ」とはスッポンのことです。栃木県の方言でスッポンのことを「コガミ」言うそうで、それが変化した言葉のようです。でも、(写真では見えませんが)葉っぱを見てもスッポンには見えないのですけど。先の尖ったところが、スッポンのシッポに似てるってことかな・・・。種子の綿毛は綿の代用として用いたり、止血効果もあるそうです。
ボタンヅル(牡丹蔓)
Clematis apiifolia キンポウゲ科
切れ込みのある3枚の小葉からなっている葉っぱの形がボタンの葉に似ていることが名前の由来です。よく似ている花に「センニンソウ」がありますが、センニンソウの葉っぱにはギザギザの切れ込みがないので見分けることは簡単です。
Clematis apiifolia キンポウゲ科
切れ込みのある3枚の小葉からなっている葉っぱの形がボタンの葉に似ていることが名前の由来です。よく似ている花に「センニンソウ」がありますが、センニンソウの葉っぱにはギザギザの切れ込みがないので見分けることは簡単です。
メドハギ(目処萩)
Lespedeza cuneata マメ科
日当たりのよい草地や道端に生えています。茎はやや木質化しています。その昔、この茎を占いに使う「筮(めどぎ)」に用いていたことが名前の由来です。そして、痩せた土地の緑化にも役立つ植物でもあります
Lespedeza cuneata マメ科
日当たりのよい草地や道端に生えています。茎はやや木質化しています。その昔、この茎を占いに使う「筮(めどぎ)」に用いていたことが名前の由来です。そして、痩せた土地の緑化にも役立つ植物でもあります
ヨウシュヤマゴボウ(洋種山牛蒡)
Phytolacca americana ヤマゴボウ科
Phytolacca americana ヤマゴボウ科
ニラ(韮)
Allium tuberosum ユリ科
暑さ、寒さにも強い植物で北海道から沖縄まで全国的に栽培されています。硫化アリルという物質が強い臭いの元ですが、ビタミンB1を体内に長く留めておく作用があるので精の付く野菜として使えます。他にも新陳代謝も促す作用もあるので、食欲増進や風邪の予防などにも効果があります。このニラはマンション内の歩道脇で見つけました。誰か植えたのかな?野菜に困ったら摘みに行こうかな。(笑)
Allium tuberosum ユリ科
暑さ、寒さにも強い植物で北海道から沖縄まで全国的に栽培されています。硫化アリルという物質が強い臭いの元ですが、ビタミンB1を体内に長く留めておく作用があるので精の付く野菜として使えます。他にも新陳代謝も促す作用もあるので、食欲増進や風邪の予防などにも効果があります。このニラはマンション内の歩道脇で見つけました。誰か植えたのかな?野菜に困ったら摘みに行こうかな。(笑)
オモダカ(面高)
Sagittaria irifoliai オモダカ科
田や沼、湿地などに生える植物です。秋になると地下に直径約1cmほどの球茎を作りますが、苦くて食べられません。これを中国で食用に改良したのがおせち料理などでよく使う「クワイ」です。
Sagittaria irifoliai オモダカ科
田や沼、湿地などに生える植物です。秋になると地下に直径約1cmほどの球茎を作りますが、苦くて食べられません。これを中国で食用に改良したのがおせち料理などでよく使う「クワイ」です。
イタドリ(虎杖)
Polygonum cuspidatum タデ科
Polygonum cuspidatum タデ科
ヒヨドリバナ(鵯花)
Eupatorium chinense var. oppositifolium キク科
8月〜10月にはなを咲かせます。ヒヨドリが鳴く頃に花が咲くのところから名前がつけられました。花はふつう白色ですが、淡紫色のものもあるそうです。
Eupatorium chinense var. oppositifolium キク科
8月〜10月にはなを咲かせます。ヒヨドリが鳴く頃に花が咲くのところから名前がつけられました。花はふつう白色ですが、淡紫色のものもあるそうです。
ゲンノショウコ(現の証拠)
Geranium nepalense subsp. thunbergii フウロソウ科
民間薬としても利用され飲むとすぐに効果が出ることから「現の証拠」と言われたのが名前の由来です。ゲンノショウコは日本を代表する民間薬で、飲み過ぎても副作用がないので勝れた整腸剤です。花の色は東日本では白花。西日本では紅紫花が多いですのですが、私が見つけたのは白花。ここは西日本です。
Geranium nepalense subsp. thunbergii フウロソウ科
民間薬としても利用され飲むとすぐに効果が出ることから「現の証拠」と言われたのが名前の由来です。ゲンノショウコは日本を代表する民間薬で、飲み過ぎても副作用がないので勝れた整腸剤です。花の色は東日本では白花。西日本では紅紫花が多いですのですが、私が見つけたのは白花。ここは西日本です。
アメリカイヌホウズキ(亜米利加犬酸漿)
Solanum americanum ナス科
Solanum americanum ナス科
タカサブロウ(高三郎)
Eclipta prostrata キク科
水田のふちなど湿地に生えていて、1cmぐらいの花をつけます。
調べて見ると帰化のアメリカタカサブロウという花もあるそうで、写真の花もひょっとするとそっちかもしれません。種の形で見分けられるそうですが、未確認です。
Eclipta prostrata キク科
水田のふちなど湿地に生えていて、1cmぐらいの花をつけます。
調べて見ると帰化のアメリカタカサブロウという花もあるそうで、写真の花もひょっとするとそっちかもしれません。種の形で見分けられるそうですが、未確認です。
ゴマナ(胡麻菜)
Aster glehnii var. hondoensis キク科
日当たりの良い草地や山地に生える多年草です。高さが1m〜1.5mにまで成長するのでキク科の中では大型の種類です。それにしてもキク科の植物って見分けにくいですよね。。。葉っぱが胡麻の葉に似ているところから付いた名前ですが、葉っぱを食べると「胡麻の味がする」のではなくて、ちょっとがっくり。(笑)でも、若い芽は天ぷらやお浸しにして食べられます。しつこいですが、胡麻の味はしませんから!(笑)
Aster glehnii var. hondoensis キク科
日当たりの良い草地や山地に生える多年草です。高さが1m〜1.5mにまで成長するのでキク科の中では大型の種類です。それにしてもキク科の植物って見分けにくいですよね。。。葉っぱが胡麻の葉に似ているところから付いた名前ですが、葉っぱを食べると「胡麻の味がする」のではなくて、ちょっとがっくり。(笑)でも、若い芽は天ぷらやお浸しにして食べられます。しつこいですが、胡麻の味はしませんから!(笑)
ハキダメギク(掃溜菊)
Galinsoga quadriradiata キク科
Galinsoga quadriradiata キク科
バジル(目箒)
Ocimum basilicum シソ科
イタリア料理では有名なハーブですね。バジリコとも呼ばれ、葉には甘い爽やかな特有の香りがあります。また、バジルの種は食物繊維の一種のグルコマンナンが豊富で水分を吸収すると半透明のゼリー状になるので、食べると胃の中で膨らんで満腹感を与えてくれるのでダイエット補助食品としても使われています。グルコマンナンとは蒟蒻に含まれるもので人間の消化酵素では消化できない食物繊維のことです。
Ocimum basilicum シソ科
イタリア料理では有名なハーブですね。バジリコとも呼ばれ、葉には甘い爽やかな特有の香りがあります。また、バジルの種は食物繊維の一種のグルコマンナンが豊富で水分を吸収すると半透明のゼリー状になるので、食べると胃の中で膨らんで満腹感を与えてくれるのでダイエット補助食品としても使われています。グルコマンナンとは蒟蒻に含まれるもので人間の消化酵素では消化できない食物繊維のことです。