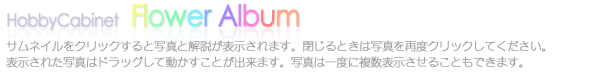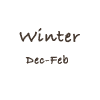ベニスモモ(紅酢桃)
Prunus salicina lindl バラ科
Prunus salicina lindl バラ科
ソメイヨシノ(染井吉野)
Prunus × yedoensis バラ科
桜と言えば代表選手は「ソメイヨシノ」ですが、ソメイヨシノは、エドヒガンザクラとザクラの交配種と言われています。そしてソメイヨシノは自身では子孫を残す能力がないので、人の手を介さないと繁殖をしていくことが出来ません。と言うことは、日本全国、あちらこちらで見かけるソメイヨシノですが、実はみ〜んな兄弟って可能性もあるのかしら。(笑)
Prunus × yedoensis バラ科
桜と言えば代表選手は「ソメイヨシノ」ですが、ソメイヨシノは、エドヒガンザクラとザクラの交配種と言われています。そしてソメイヨシノは自身では子孫を残す能力がないので、人の手を介さないと繁殖をしていくことが出来ません。と言うことは、日本全国、あちらこちらで見かけるソメイヨシノですが、実はみ〜んな兄弟って可能性もあるのかしら。(笑)
シダレザクラ(枝垂桜)
Prunus pendula バラ科
Prunus pendula バラ科
ヒメヤマツツジ(姫山躑躅)
Rhododendron kaemperi Planch. var. tubiflorum Komatsu ツツジ科
Rhododendron kaemperi Planch. var. tubiflorum Komatsu ツツジ科
コバノミツバツツジ(小葉三葉躑躅)
Rhododendron reticulatum ツツジ科
Rhododendron reticulatum ツツジ科
クモマグサ(雲間草)
Saxifraga rosacea ユキノシタ科
Saxifraga rosacea ユキノシタ科
カラスノエンドウ(烏野豌豆)
Vicia sepium マメ科
Vicia sepium マメ科
ヒメオドリコソウ(姫踊子草)
Lamium purpureum シソ科
Lamium purpureum シソ科
ハナミズキ(花水木)
Cornus florida ミズキ科
Cornus florida ミズキ科
ツクバネウツギ(衝羽根空木)
Abelia spathulata スイカズラ科
ターシャ・テューダーの「喜びは創りだすもの」だと思いますが、その中でターシャが庭のウツギの枝を切って花瓶に活けている場面がありました。この花をみると、そのシーンとターシャを思い出します。ターシャのお庭にあるも木。それがうちの近所でも見られるなんて、ちょっと嬉しいです。
Abelia spathulata スイカズラ科
ターシャ・テューダーの「喜びは創りだすもの」だと思いますが、その中でターシャが庭のウツギの枝を切って花瓶に活けている場面がありました。この花をみると、そのシーンとターシャを思い出します。ターシャのお庭にあるも木。それがうちの近所でも見られるなんて、ちょっと嬉しいです。
ノアザミ(野薊)
Cirsium japonicum キク科
Cirsium japonicum キク科
ユウゲショウ(夕化粧)
Oenothera rosea アカバナ科
Oenothera rosea アカバナ科
ナワシロイチゴ(苗代苺)
Rubus parvifoius バラ科
Rubus parvifoius バラ科
ムシトリナデシコ(虫取撫子)
Silene armeria ナデシコ科
ヨーロッパ原産の帰化植物です。茶色っぽくなった茎上部の節下には粘液が出ていて、虫がくっつくことがありますが、この植物は食虫植物ではありません。ただ付着しているだけです。そのことから「ハエトリナデシコ」と言う別名もあります。
Silene armeria ナデシコ科
ヨーロッパ原産の帰化植物です。茶色っぽくなった茎上部の節下には粘液が出ていて、虫がくっつくことがありますが、この植物は食虫植物ではありません。ただ付着しているだけです。そのことから「ハエトリナデシコ」と言う別名もあります。
ムラサキケマン(紫華鬘)
Corydalis incisa ケシ科
道端などのやや湿ったところに生え、4月から6月にかけて花を咲かせ、高さ20〜50cmになります。ムラサキケマンを感じで書くと「紫華鬘」。紫色のケマンソウの意味ですが、華鬘とは仏堂の欄間にかける透かし彫りのある仏具のことだそうです。この花のどんなところと関係があるのでしょうね。
Corydalis incisa ケシ科
道端などのやや湿ったところに生え、4月から6月にかけて花を咲かせ、高さ20〜50cmになります。ムラサキケマンを感じで書くと「紫華鬘」。紫色のケマンソウの意味ですが、華鬘とは仏堂の欄間にかける透かし彫りのある仏具のことだそうです。この花のどんなところと関係があるのでしょうね。
ノハラナデシコ(野原撫子)
Dianthus armeria ナデシコ科
ヨーロッパ原産の帰化植物です。国内で発見されたのは約40年ほど前ですが、今では本州や九州で帰化しています。
Dianthus armeria ナデシコ科
ヨーロッパ原産の帰化植物です。国内で発見されたのは約40年ほど前ですが、今では本州や九州で帰化しています。
イヌコモチナデシコ(犬子持撫子)
Petrorhagia nanteulii ナデシコ科
Petrorhagia nanteulii ナデシコ科
ムラサキカタバミ(紫片喰)
Oxalis corymbosa カタバミ科
Oxalis corymbosa カタバミ科
イモカタバミ(芋片喰)
Oxalis articulata カタバミ科
南アフリカ原産の多年草です。観賞用に栽培されているほかに、人家周辺で野生化されているものもあります。人家周辺でよく見かけられる「ムラサキカタバミ」と非常によく似ていますが、イモカタバミの花の中心は濃い赤色で雄しべの先の葯は黄色なのに対し、「ムラサキカタバミ」は中心部が淡い黄緑色で雄しべの葯は白色です。でも、ぱっと見たら区別が付きにくいですよね。
Oxalis articulata カタバミ科
南アフリカ原産の多年草です。観賞用に栽培されているほかに、人家周辺で野生化されているものもあります。人家周辺でよく見かけられる「ムラサキカタバミ」と非常によく似ていますが、イモカタバミの花の中心は濃い赤色で雄しべの先の葯は黄色なのに対し、「ムラサキカタバミ」は中心部が淡い黄緑色で雄しべの葯は白色です。でも、ぱっと見たら区別が付きにくいですよね。
ホトケノザ(仏の座)
Lamium amplexicaule シソ科
Lamium amplexicaule シソ科
トウバナ(塔花)
Clinopodium gracile シソ科
Clinopodium gracile シソ科
シラン(紫蘭)
Bletilla striata ラン科
乾燥や暑さにも強く放っておいてもどんどん増える植物です。こんなに強いお花ですが、野生のシランは準絶滅危惧種になっています。もしも、この強さのお陰で園芸種が増えて野生化してしまった場合は、どういうことになるのでしょうか?それでも絶滅危惧種?
Bletilla striata ラン科
乾燥や暑さにも強く放っておいてもどんどん増える植物です。こんなに強いお花ですが、野生のシランは準絶滅危惧種になっています。もしも、この強さのお陰で園芸種が増えて野生化してしまった場合は、どういうことになるのでしょうか?それでも絶滅危惧種?
ヒゲナデシコ(髭撫子)
Dianthus barbatus ナデシコ科
Dianthus barbatus ナデシコ科
カリン(花梨)
Chaenomeles sinensis バラ科
Chaenomeles sinensis バラ科
ハナエンジュ(花槐)
Robinia hispida マメ科
北アメリカ原産の落葉低木。排気ガスにも強く、伸びすぎないことから街路樹に植えられているところも多いです。また花や蕾は「槐花」と言う名前の生薬で止血作用があります。
Robinia hispida マメ科
北アメリカ原産の落葉低木。排気ガスにも強く、伸びすぎないことから街路樹に植えられているところも多いです。また花や蕾は「槐花」と言う名前の生薬で止血作用があります。
ベニウツギ(紅空木)
Weigela hortensis スイカズラ科
学名は「卯木」ですが、幹を折ってみると中は中空なので「空木」が名前の由来とも言われています。また、別名「卯の花」とも呼ばれています。旧暦4月(卯月)に咲くことからその名があります。旧暦の4月は現在の5月。初夏の花ということで夏の季語として、万葉集・古今和歌集・枕草子歌などで、古くから歌や句に詠まれてきました。それもホトトギスとの組み合わせが多いようです。新しいところでは、明治29年(1896)に小学校5年生用の音楽教科書『新編教育唱歌集(第五集)』に掲載された、童謡の「夏は来ぬ 佐々木信綱作詞・小山作之助作曲」があります。
♪ 卯(う)の花の匂う 垣根(かきね)に 時鳥(ほととぎす) 早(はや)も来(き)鳴きて 忍(しの)び音(ね)もらす 夏は来ぬ ♪
Weigela hortensis スイカズラ科
学名は「卯木」ですが、幹を折ってみると中は中空なので「空木」が名前の由来とも言われています。また、別名「卯の花」とも呼ばれています。旧暦4月(卯月)に咲くことからその名があります。旧暦の4月は現在の5月。初夏の花ということで夏の季語として、万葉集・古今和歌集・枕草子歌などで、古くから歌や句に詠まれてきました。それもホトトギスとの組み合わせが多いようです。新しいところでは、明治29年(1896)に小学校5年生用の音楽教科書『新編教育唱歌集(第五集)』に掲載された、童謡の「夏は来ぬ 佐々木信綱作詞・小山作之助作曲」があります。
♪ 卯(う)の花の匂う 垣根(かきね)に 時鳥(ほととぎす) 早(はや)も来(き)鳴きて 忍(しの)び音(ね)もらす 夏は来ぬ ♪
サクラソウ(桜草)
Primula sieboldii サクラソウ科
日本原産のお花です。野生のサクラソウは、盗掘や自然破壊で少なくなり、数種類の「日本サクラソソウ」は絶滅危惧種にも指定されています。
Primula sieboldii サクラソウ科
日本原産のお花です。野生のサクラソウは、盗掘や自然破壊で少なくなり、数種類の「日本サクラソソウ」は絶滅危惧種にも指定されています。
シバザクラ(芝桜)
Phlox subulata ハナシノブ科
Phlox subulata ハナシノブ科
シモツケ(下野)
Spiraea japonica バラ科
落葉低木で花は5月〜8月に咲きます。名前の由来は栃木県の下野で最初に発見されたからだそうです。花言葉は自由。
Spiraea japonica バラ科
落葉低木で花は5月〜8月に咲きます。名前の由来は栃木県の下野で最初に発見されたからだそうです。花言葉は自由。
ヤナギハナガサ(柳花笠)
Verbena bonariensis クマツヅラ科
南米原産の帰化植物で、観賞用に持ち込まれたものが野生化したようです。スーっとした背丈は1mほどで、枝の先に花笠のような花を付け、葉っぱは柳のように細く、花がバーベナに似ているところから三尺バーベナとも呼ばれます。
Verbena bonariensis クマツヅラ科
南米原産の帰化植物で、観賞用に持ち込まれたものが野生化したようです。スーっとした背丈は1mほどで、枝の先に花笠のような花を付け、葉っぱは柳のように細く、花がバーベナに似ているところから三尺バーベナとも呼ばれます。
ネジバナ(捩花)
Spiranthes sinensis var. amoena ラン科
名前の由来の「ねじれて花がつくことから」でも分かるように、5mmほどの花をらせん状に付けます。この巻き方には決まりはありません。右巻き、左巻き、どちらもあります。
Spiranthes sinensis var. amoena ラン科
名前の由来の「ねじれて花がつくことから」でも分かるように、5mmほどの花をらせん状に付けます。この巻き方には決まりはありません。右巻き、左巻き、どちらもあります。
ヘクソカズラ(屁糞葛)
Paederia scandensx アカネ科
Paederia scandensx アカネ科
マツバギク(松葉菊)
Lampranthus spectabilis ツルナ科
Lampranthus spectabilis ツルナ科
アレチヌスビトハギ(荒地盗人萩)
Desmodium paniculatum マメ科
Desmodium paniculatum マメ科
マルバハギ(丸葉萩)
Lespedeza cyrtobotrya マメ科
Lespedeza cyrtobotrya マメ科
コスモス(秋桜)
Cosmos bipinnatus キク科
原産地はメキシコの高原地帯で、日本には明治時代に入って来ました。日当たりと水はけが良ければ痩せた土地でもよく生育します。儚げな花に見えるコスモスですが、見た目とは違い台風などで倒れても、茎の途中から根を出し、また立ち上がって花をつけると言う、実は強い植物でもあります。
Cosmos bipinnatus キク科
原産地はメキシコの高原地帯で、日本には明治時代に入って来ました。日当たりと水はけが良ければ痩せた土地でもよく生育します。儚げな花に見えるコスモスですが、見た目とは違い台風などで倒れても、茎の途中から根を出し、また立ち上がって花をつけると言う、実は強い植物でもあります。
ミゾソバ(溝蕎麦)
Polygonum thunbergii タデ科
Polygonum thunbergii タデ科
ホトトギス(杜鵑草)
Tricyrtis hirta ユリ科
山地や傾斜地の日射の弱いところに生える植物です。葉の脇に白色で濃紅紫色の斑点のある花を咲かせます。その斑点が鳥のホトトギスの胸にある斑点模様に似ていることが名前の由来にもなっています。
Tricyrtis hirta ユリ科
山地や傾斜地の日射の弱いところに生える植物です。葉の脇に白色で濃紅紫色の斑点のある花を咲かせます。その斑点が鳥のホトトギスの胸にある斑点模様に似ていることが名前の由来にもなっています。
ホソバヒメミソハギ(細葉姫禊萩)
Ammannia coccinea ミソハギ科
田や沼地などの水辺に生えるアメリカ大陸原産の帰化植物です。紫紅色の4mmほどで可愛らしい花を咲かせますが、この花びらの色が落ちやすいことから、花言葉が「美人薄命」のようです。
Ammannia coccinea ミソハギ科
田や沼地などの水辺に生えるアメリカ大陸原産の帰化植物です。紫紅色の4mmほどで可愛らしい花を咲かせますが、この花びらの色が落ちやすいことから、花言葉が「美人薄命」のようです。
ミゾカクシ(溝隠)
Lobelia chinensis キキョウ科
田のあぜや湿地などに生える有毒植物です。知らないとは怖いことで、写真を撮っている時には有毒植物だなんて知りませんでした。平気で触ってたと思う。。。食べたりすると、呼吸麻痺やけいれんなどを引き起こすらしいので触っただけでは大丈夫かもしれませんが、汁が手に付き、それが万が一口にでも入ったら症状が出るかもしれませんよね。安易に知らない花は触ってはいけないと、今頃ですが思っています。気を付けよ。
Lobelia chinensis キキョウ科
田のあぜや湿地などに生える有毒植物です。知らないとは怖いことで、写真を撮っている時には有毒植物だなんて知りませんでした。平気で触ってたと思う。。。食べたりすると、呼吸麻痺やけいれんなどを引き起こすらしいので触っただけでは大丈夫かもしれませんが、汁が手に付き、それが万が一口にでも入ったら症状が出るかもしれませんよね。安易に知らない花は触ってはいけないと、今頃ですが思っています。気を付けよ。
ゲンノショウコ(現の証拠)
Geranium nepalense ssp. thunbergii フウロソウ科
Geranium nepalense ssp. thunbergii フウロソウ科
センニチコウ(千日紅)
Gomphrena globosa ヒユ科
Gomphrena globosa ヒユ科
イヌタデ(犬蓼)
Polygonum longisetum タデ科
道端や畑に生える1年草。料理に使われる「タテ酢」は、ヤナギタデの葉をすりおろし香辛料として酢に混ぜて作ります。お刺身などに添えられている紅タデは、ヤナギタデの芽です。「タデ」とは、葉っぱを噛むと辛くて口の中が、ただれるという所から「タデ」という言葉が生まれたと言われています。しかし、イヌタデは葉っぱを噛んでも辛みはありません。利用価値のないタデの意味でイヌタデ(犬蓼)と呼ばれるようになりました。が!なぜ利用価値が無いと言うのが「”犬”蓼」なんでしょう?こちらの「要ぬ」を使うのなら分かるのだけど。犬が可哀想です。
Polygonum longisetum タデ科
道端や畑に生える1年草。料理に使われる「タテ酢」は、ヤナギタデの葉をすりおろし香辛料として酢に混ぜて作ります。お刺身などに添えられている紅タデは、ヤナギタデの芽です。「タデ」とは、葉っぱを噛むと辛くて口の中が、ただれるという所から「タデ」という言葉が生まれたと言われています。しかし、イヌタデは葉っぱを噛んでも辛みはありません。利用価値のないタデの意味でイヌタデ(犬蓼)と呼ばれるようになりました。が!なぜ利用価値が無いと言うのが「”犬”蓼」なんでしょう?こちらの「要ぬ」を使うのなら分かるのだけど。犬が可哀想です。
ヤエカンコウ(八重寒紅)
Prunusu mume cv. Yaekankou バラ科
早咲きの寒梅種で12月末頃から咲き始めるらしいのですが、近所に咲いているヤエカンコウが年末に咲いているのは見たことがないと思います。昨年でも1月の中旬くらいだったと思います。地域によるのかなあ?まあ、いずれにせよ、毎年、きれいな花を咲かせ楽しませてくれるのですから気にしな〜い。そして、いよいよ色々な梅の花も咲き始め、暦の上だけの春だけじゃなくて、「本当に春はすぐそこまで来ているのだなあ。」としみじみと思い、冬眠から覚める準備をしなくちゃ!とも思う私です。
Prunusu mume cv. Yaekankou バラ科
早咲きの寒梅種で12月末頃から咲き始めるらしいのですが、近所に咲いているヤエカンコウが年末に咲いているのは見たことがないと思います。昨年でも1月の中旬くらいだったと思います。地域によるのかなあ?まあ、いずれにせよ、毎年、きれいな花を咲かせ楽しませてくれるのですから気にしな〜い。そして、いよいよ色々な梅の花も咲き始め、暦の上だけの春だけじゃなくて、「本当に春はすぐそこまで来ているのだなあ。」としみじみと思い、冬眠から覚める準備をしなくちゃ!とも思う私です。